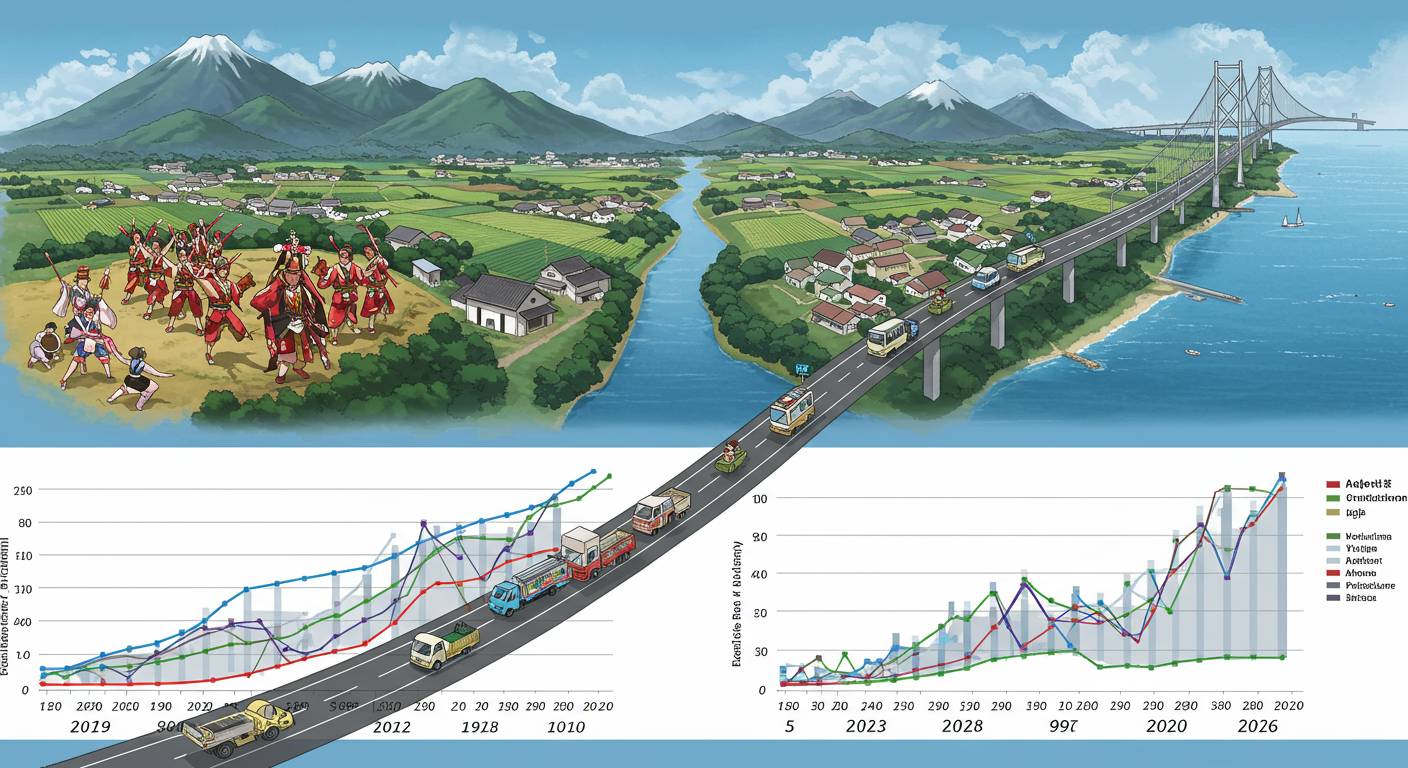
「徳島・香川で車なし生活は可能?登録台数から読み解く地方の本当の交通事情」
みなさん、こんにちは!今日は四国の徳島県と香川県の自動車登録台数から見える地方の交通事情について掘り下げていきます。都会では電車やバスが充実していて車がなくても生活できますが、地方ではどうでしょうか?
実は徳島・香川の自動車保有率は全国平均を大きく上回っているんです。これって一体なぜ?公共交通機関の利便性?それとも生活スタイルの違い?データから見える地方暮らしの実態に迫ります!
車の買い替えや田舎暮らしを考えている方、地方の交通事情に興味がある方は必見です。大阪で車を売却するなら安心の査定サービスも紹介していますので、ぜひ最後までお読みください!
四国地方、特に徳島県と香川県の自動車登録台数を見ると、地方の交通事情が浮き彫りになります。徳島県の人口約72万人に対し、自動車保有台数は約57万台。香川県は人口約95万人に対して約70万台が登録されています。これは両県とも1人あたり0.7〜0.8台という高い保有率を示しています。都市部では0.3〜0.4台程度が一般的であることを考えると、いかに地方で車が必要不可欠かがわかるでしょう。
「車がないと生活できない」という言葉は、四国ではまさに現実です。JR四国の路線は限られており、バスの本数も都市部と比較すると少ないのが実情。特に徳島県南部や香川県の島嶼部では公共交通の空白地帯も存在します。こうした地域では自家用車は単なる移動手段ではなく、生活インフラとしての役割を担っています。
興味深いのは車種の傾向です。四国では軽自動車の割合が全国平均より約5%高く、徳島県では登録車両の約40%が軽自動車です。これは税金や維持費の負担を考慮した実用性重視の選択と言えるでしょう。また、高齢化が進む地域では、運転しやすい小型車や軽自動車の需要が特に高まっています。
瀬戸大橋開通以降、香川県では本州との行き来が容易になったことで自動車文化にも変化が見られます。特に高松市周辺では比較的新しい車両の割合が高く、県外ナンバーの車も多く見かけるようになりました。一方、徳島県では愛車を長く大切に乗り続ける傾向があり、10年以上の車両比率は全国平均を上回っています。
地方創生が叫ばれる中、自動車は地方の生活を支える重要な要素であり続けています。電気自動車への移行や自動運転技術の発展が今後どのように地方の車事情に影響するのか、徳島・香川両県の自動車登録台数の推移は引き続き注目すべき指標となるでしょう。
徳島県と香川県の自動車登録台数を見ると、地方の交通事情の実態が浮き彫りになります。四国地方に位置するこれらの県では、1世帯あたりの自動車保有台数が全国平均を上回っており、徳島県では約1.6台、香川県では約1.5台となっています。
特筆すべきは、人口減少が進む中でも登録台数がそれほど減少していないという事実です。これは地方では「車がないと生活できない」現実を如実に表しています。公共交通機関の本数削減や路線廃止が相次ぐ中、自家用車は単なる移動手段ではなく、生活インフラとしての役割を担っているのです。
徳島県の山間部では、最寄りのスーパーまで車で30分以上かかる地域も珍しくありません。香川県でも高松市中心部を除けば、日常の買い物や通院に車は必須アイテムです。興味深いのは軽自動車の割合が両県とも50%前後と高いこと。経済的な理由だけでなく、狭い道が多い地域性も影響しています。
また、両県では高齢ドライバーの比率が年々上昇。75歳以上のドライバーが徳島では全体の15%、香川では14%を占めるまでになっています。免許返納後の移動手段確保が地域課題となる中、デマンド交通やシェアリングサービスの整備が進められていますが、まだ十分とは言えない状況です。
都会では当たり前の「車なし生活」が、徳島・香川では現実的ではないという事実。自動車登録台数という冷たい数字の裏には、地方の交通インフラの脆弱さと、それに適応して生きる人々の知恵が隠されているのです。
地方に住む人々にとって、自家用車は単なる移動手段ではなく、生活を支える重要なライフラインです。特に徳島県と香川県のデータを見ると、その実態が鮮明に浮かび上がってきます。
徳島県の自動車保有台数は人口減少にも関わらず、ほぼ横ばい状態が続いています。これは1人あたりの自動車保有台数が実質的に増加していることを意味します。具体的には、徳島県では1世帯あたり約1.5台の車を所有しているというデータがあります。
一方、香川県でも同様の傾向が見られます。高松市のような都市部でさえ、公共交通機関だけでは日常生活を送ることが難しく、多くの世帯が複数の自動車を所有しています。
この背景には、地方特有の「時間距離」の問題があります。例えば、徳島市から那賀町木頭地区までは車で約2時間。この距離を公共交通機関だけでカバーするのは現実的ではありません。JR四国の路線縮小や、徳島バス、琴平バスなどの路線バスの減便も、車依存をさらに強めています。
特筆すべきは高齢者の車依存度です。徳島県・香川県ともに高齢化率が30%を超える中、70歳以上のドライバーが関わる事故件数は全国平均より高い水準にあります。しかし、車がなければ病院に行くことすら困難な地域も多く、「免許返納したくてもできない」というジレンマが生じています。
また、EV(電気自動車)の普及率は全国平均を下回っていますが、これには充電インフラの不足だけでなく、長距離移動が日常的な地方の生活スタイルとEVの航続距離の問題も関係しています。
こうしたデータから見えてくるのは、都市部と地方の「モビリティ格差」です。コンパクトシティ政策や公共交通の再構築なしに、単純な「脱車社会」を進めることは、地方の生活基盤を揺るがしかねません。
徳島・香川両県の自動車登録データは、地方における交通政策の難しさと、車に依存せざるを得ない地方の現実を如実に物語っています。